◆うろこ新聞 目次◆前頁(うろこ新聞 2001年9月6日号)◆次頁(うろこ新聞 2001年9月3日号)◆
■Shimirin's HomePage■Urokocity■SiteMap■
|
|

|
うろこ新聞 2001年9月5日号

1カ月ぐらい「うろこ新聞」を更新してきて、そのうちに秋になっていく。秋の空は、すぐ詩になる。いろいろな人が詩にしてきた。僕も秋が好きだった。柘榴が割れて、きれいなざらざらした実が見えるころ、とんぼが空いっぱいに飛ぶころ、雑木林は落ち着いて「恋」に「恋」する季節になったものだ。とはいっても、恋する対象がいなかったのだが。
東京に来て、割れた柘榴なんかやたらと見ることができないので、季節の移ろいの裏にあった野暮なものが前面に出てくると、「失われた時」を一枚一枚めくることになる。
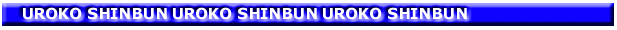
【倉田良成の解酲子飲食 22】
酎論再び
かつてこのような評価を受けた焼酎ではあるが、いまは事情が異なるというのは先申したとおりであるけれど、だがかつてという範疇で考えてみても、焼酎というのはなかなか味のある性格を持った酒だったのではなかろうか。清酒が儀礼や祭祀に欠かせないいわばハレのものだとすれば、焼酎はわれわれの先祖のケの部分で飲み継がれてきた酒だという気がする。落語で焼酎の話は珍しいが、庭職人の八だか熊だかが旦那に進められて酔態を呈する柳蔭という酒は、本直しともいって味醂を焼酎で割ったもので、小さん師が得意とするこの噺の柳蔭はいかにも強くて甘くて利きそうで、観ているこっちまで一緒に舌なめずりをしたくなってくる。また、石川淳の「諸国奇人伝」に伊那の井月と出ている乞食俳人は、腰に瓢箪をぶら下げてそれが焼酎で満たされてあるときには「千両、千両」とつぶやいて、果ては野垂れ死んだそうだというこんな話を読むにつけ、世で最も下等とされる酒がときに最も浮世離れした光彩を放つような気がしてならない。私の偏見をひとつ言えば、清酒は文士という感じだが、詩人には焼酎が似合う。西脇順三郎の詩の「神酒を入れるヒョウタン」(「秋」)に入った神酒とは、オミキではなく神酒と読むべきで、あれはたぶん焼酎のことをいっているのだ。両人対酌山花開、一杯一杯復一杯、というところか。
井月ものまずカ のまずヨ 菊の酒 夷斎
|
|
| ◆うろこ新聞 目次◆前頁(うろこ新聞 2001年9月6日号)◆次頁(うろこ新聞 2001年9月3日号)◆
|
|
|
■Shimirin's HomePage■Urokocity■SiteMap■
|